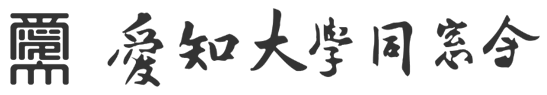東方斎荒尾精先覚顕彰碑と殉難九烈士顕彰碑(熊野若王子神社・京都市左京区)
荒尾精先生と東亜同文書院
荒尾精先生の碑文によせてー
ここの解説板では、正面の荒尾精への追悼碑文および右隣に設けられた霞山会による解説板の中に記された荒尾精の構想により実現した東亜同文書院について紹介させていただく。
「東亜同文書院」は、荒尾精が私塾「漢口楽善堂」を発展させて一八九〇年(明治二十三年)上海に開設した「日清貿易研究所」の経験をふまえ構想した世界初の国際ビジネススクールであった。
その直前に近衛篤麿は清国両江総督劉坤一に会い、その承認の上で日清両国の学生を一緒に教育する南京同文書院を開設したが、義和団の乱を避けて上海へ移動し、折しも上海で荒尾精が構想したビジネススクールを実現しつつあった根津一の学校と統合し、一九〇一年(明治三十四年)に「東亜同文書院」を誕生させた。
近衛篤麿は南京同文書院開設時に、各府県の知事を巡り、各府県から数名の学生を府県給費生として派遣依頼をする方法を採ったが、東亜同文書院への入学生にもこの方式を採用し、全国からすぐれた旧制中学、商業学校卒業生を集め、勉学や進取の気性に富む若者に新しい進路を開いた。そして徹底した清語と英語の教育を軸に、幅広い貿易関係の専門科目群を習得させ、日清間の貿易実務者の養成を図った。それは荒尾精がそれより前、三年半に及ぶ清国で実地に会得した商取引経験をふまえ、実践と原理を組合せた独自の教育システムの実現であった。
そのうちの実践では「大旅行」と称する現地踏査による調査研究法が学生からの要望で設けられ、特筆された。自由に自力で中国を見聞したいという熱意のあふれた学生たちは、四~六人ほどの各グループを編成し、卒論になる踏査期間は三、四カ月、徒歩中心の踏査旅行を行った。その範囲は中国本土から満州、東南アジアに及び、二〇世紀前半期のこの一帯の地域像を七百コースで記録し、その成果は『支那経済全書』(全一二巻)、『支那省別全誌』(全十八巻)、『新修支那省別全誌』(九巻目で戦時により中断)として広く公刊され、日本初そして世界初の地域研究のパイオニアとなった。
この体験は中国はじめ各地の人々との交流も含め、書院生のその後の人生に大きな自信と誇りをもたらした。それは、卒業生の就業にもあらわれ、起業も含めた実業界を中心に、外交、報道、教育、学界など、戦前は勿論、戦後引揚げ帰国したのちも、商社などの国際化にも寄与し、戦後日本の高度経済成長を中心的に支えるなど幅広い活躍を示した。
ところで、敗戦により一九四五年(昭和二十年)、上海の東亜同文書院大学は一旦閉学せざるを得なくなったが、その直前に開設されていた呉羽分校(富山県)は吉田茂外相の認可により再開復活した。しかし、この年末、経営母体東亜同文会の会長であった近衛文麿が自決し、同会はGHQにより解散され、書院大学の分校も閉学となった。
その一方、まだ上海に留っていた最後の本間喜一学長は、第一次世界大戦後の超インフレ時代のドイツ留学での経験を生かし、紙幣すべてを食糧や車、油、金などに換え、中国各地から上海へ帰校してくる書院生や教職員を経済的に支援し、日本への帰国を待った。そんな折、呉羽分校閉学を知り、急遽代替地を求めるよう分校関係者へ要請し、その結果、分校神谷教授の尽力で愛知県豊橋市の旧陸軍予備士官学校跡が確保された。
こうして翌一九四六年春、書院生の学籍簿や成績簿とともに本間学長一行が帰国すると、呉羽校舎でも検討されていた新大学構想実現に着手した。そして六大都市以外で初めての「旧制大学」を受け入れる豊橋市の全面的協力のもと、書院時代の教員と学生を軸に、新たに台北、京城帝大の教員そして第一線の研究者や外地および国内他校からの学生も加え、一九四六年(昭和二十一年)十一月十五日、「知を愛する」意を込めて「旧制大学」としての「愛知大学」を誕生させた。しかも、GHQの支配下にあって設立主旨には堂々と「国際人の養成」を掲げて書院の背景を示し、また最初の地方都市への立地に「地域社会への貢献」を掲げた。
とはいえ、敗戦直後無一文で引揚げてきた状況下で、新大学を実現することは、資金、施設、図書などの整備に、言い尽くせないドラマチックな歴史も刻んできた。
現在、愛知大学は豊橋、名古屋(笹島、車道)の三校舎に法、経済、経営、文、現代中国、国際コミュニケーション、地域政策の六学部と短大を展開し、一万人の学生が学んでいる。うち、現代中国学部と大学院中国研究科は日本唯一の存在であり、他の関係専攻とともに東亜同文書院の血脈が流れている。
また、「愛知大学東亜同文書院大学記念センター」が設けられ、書院の顕彰と研究をすすめ、書院の志を今日に伝えようとしている。
以上、荒尾精先生の構想を軸に、それを支え実現した近衛篤麿、根津一の三先覚の偉業も顕彰し、荒尾を讃えた近衛のこの碑文に敬意を表し、亜同文書院とそれをルーツとする愛知大学誕生に至る経緯を紹介させていただいた。
<付記> 建立以来苔蒸して解読が困難となっていたこの碑を今日在る姿にしたのは、三田良信氏(書院四十二期生)父子のご尽力による。
二〇二五年(令和七年)十一月
愛知大学
ここの解説板では、正面の荒尾精への追悼碑文および右隣に設けられた霞山会による解説板の中に記された荒尾精の構想により実現した東亜同文書院について紹介させていただく。
「東亜同文書院」は、荒尾精が私塾「漢口楽善堂」を発展させて一八九〇年(明治二十三年)上海に開設した「日清貿易研究所」の経験をふまえ構想した世界初の国際ビジネススクールであった。
その直前に近衛篤麿は清国両江総督劉坤一に会い、その承認の上で日清両国の学生を一緒に教育する南京同文書院を開設したが、義和団の乱を避けて上海へ移動し、折しも上海で荒尾精が構想したビジネススクールを実現しつつあった根津一の学校と統合し、一九〇一年(明治三十四年)に「東亜同文書院」を誕生させた。
近衛篤麿は南京同文書院開設時に、各府県の知事を巡り、各府県から数名の学生を府県給費生として派遣依頼をする方法を採ったが、東亜同文書院への入学生にもこの方式を採用し、全国からすぐれた旧制中学、商業学校卒業生を集め、勉学や進取の気性に富む若者に新しい進路を開いた。そして徹底した清語と英語の教育を軸に、幅広い貿易関係の専門科目群を習得させ、日清間の貿易実務者の養成を図った。それは荒尾精がそれより前、三年半に及ぶ清国で実地に会得した商取引経験をふまえ、実践と原理を組合せた独自の教育システムの実現であった。
そのうちの実践では「大旅行」と称する現地踏査による調査研究法が学生からの要望で設けられ、特筆された。自由に自力で中国を見聞したいという熱意のあふれた学生たちは、四~六人ほどの各グループを編成し、卒論になる踏査期間は三、四カ月、徒歩中心の踏査旅行を行った。その範囲は中国本土から満州、東南アジアに及び、二〇世紀前半期のこの一帯の地域像を七百コースで記録し、その成果は『支那経済全書』(全一二巻)、『支那省別全誌』(全十八巻)、『新修支那省別全誌』(九巻目で戦時により中断)として広く公刊され、日本初そして世界初の地域研究のパイオニアとなった。
この体験は中国はじめ各地の人々との交流も含め、書院生のその後の人生に大きな自信と誇りをもたらした。それは、卒業生の就業にもあらわれ、起業も含めた実業界を中心に、外交、報道、教育、学界など、戦前は勿論、戦後引揚げ帰国したのちも、商社などの国際化にも寄与し、戦後日本の高度経済成長を中心的に支えるなど幅広い活躍を示した。
ところで、敗戦により一九四五年(昭和二十年)、上海の東亜同文書院大学は一旦閉学せざるを得なくなったが、その直前に開設されていた呉羽分校(富山県)は吉田茂外相の認可により再開復活した。しかし、この年末、経営母体東亜同文会の会長であった近衛文麿が自決し、同会はGHQにより解散され、書院大学の分校も閉学となった。
その一方、まだ上海に留っていた最後の本間喜一学長は、第一次世界大戦後の超インフレ時代のドイツ留学での経験を生かし、紙幣すべてを食糧や車、油、金などに換え、中国各地から上海へ帰校してくる書院生や教職員を経済的に支援し、日本への帰国を待った。そんな折、呉羽分校閉学を知り、急遽代替地を求めるよう分校関係者へ要請し、その結果、分校神谷教授の尽力で愛知県豊橋市の旧陸軍予備士官学校跡が確保された。
こうして翌一九四六年春、書院生の学籍簿や成績簿とともに本間学長一行が帰国すると、呉羽校舎でも検討されていた新大学構想実現に着手した。そして六大都市以外で初めての「旧制大学」を受け入れる豊橋市の全面的協力のもと、書院時代の教員と学生を軸に、新たに台北、京城帝大の教員そして第一線の研究者や外地および国内他校からの学生も加え、一九四六年(昭和二十一年)十一月十五日、「知を愛する」意を込めて「旧制大学」としての「愛知大学」を誕生させた。しかも、GHQの支配下にあって設立主旨には堂々と「国際人の養成」を掲げて書院の背景を示し、また最初の地方都市への立地に「地域社会への貢献」を掲げた。
とはいえ、敗戦直後無一文で引揚げてきた状況下で、新大学を実現することは、資金、施設、図書などの整備に、言い尽くせないドラマチックな歴史も刻んできた。
現在、愛知大学は豊橋、名古屋(笹島、車道)の三校舎に法、経済、経営、文、現代中国、国際コミュニケーション、地域政策の六学部と短大を展開し、一万人の学生が学んでいる。うち、現代中国学部と大学院中国研究科は日本唯一の存在であり、他の関係専攻とともに東亜同文書院の血脈が流れている。
また、「愛知大学東亜同文書院大学記念センター」が設けられ、書院の顕彰と研究をすすめ、書院の志を今日に伝えようとしている。
以上、荒尾精先生の構想を軸に、それを支え実現した近衛篤麿、根津一の三先覚の偉業も顕彰し、荒尾を讃えた近衛のこの碑文に敬意を表し、亜同文書院とそれをルーツとする愛知大学誕生に至る経緯を紹介させていただいた。
<付記> 建立以来苔蒸して解読が困難となっていたこの碑を今日在る姿にしたのは、三田良信氏(書院四十二期生)父子のご尽力による。
二〇二五年(令和七年)十一月
愛知大学
九烈士の碑文について
ここ熊野若王子神社境内に建つ近衛篤麿による荒尾精への巨大な追悼碑が正面を見据えた先に建っているのが、荒尾精と根津一によって建立されたこの清殉難九烈士」への鎮魂、顕彰碑である。
近衛篤麿の撰文による荒尾精への追悼碑文にも記されているように、荒尾精は当初軍人教育を受けたが、隣国の清が西欧列強に蚕食されつつある実態を知り、その対抗策は日清間の貿易を発展させ相互の経済力を強めることだとの考えに至った。こうして一八八六年(明治十九年)、念願かなって単身上海へ渡った荒尾は、すでに上海で国際商人として活躍していた日本人、岸田吟香の協力援助により、長江を遡った漢口に岸田の支店「漢口楽善堂」を開店し、岸田から提供された目薬や書籍、雑貨を販売し、清国での商取引体験を始めた。
そのさい、荒尾は、一八七七年(明治十年)に西南戦争で敗れた薩摩と肥後の若者や幕末に官軍に敗れた会津藩などの若者で、日本での出世をあきらめ渡してきた二十余名ほどを「漢⊂楽善堂」のメンバーとして集め、清国の商慣習を体験させるとともに商品販売や関係情報を収集整理もする私塾も設けた。商人となった若者達は商品を背負い各地へ出かけたが、不審者への警備が厳しい中、命を落したり、行方不明者が次々に出て、この試みには困難も多かった。
しかし、荒尾が三年半に及ぶこの清国での滞在中に収集した情報は多く、それらはこのあと盟友根津一(のち書院初代院長)の手で編纂され、『清国涌商綜覧』という商業地理的大著にまとめられ刊行された。初めて清国の実態を知った読者の評判となり、ベストセラーとなったほどであった。
荒尾はこれらの実績をふまえ、帰国後本格的な日清間の貿易事業人養成のための商社と学業の設立構想を明治政府に提案し、農商務省など関係大臣の支持を得た。そこで荒尾は早速全国を遊説し、日清間の貿易の重要性と将来性を学徒たちに説き、志願者を求め、うち選抜した一五〇人を連れ、関係者一同と共に上海へ向った。
しかし、折から支持してくれた岩村農商務省大臣は突然病気で辞任し、内閣も解散となり、荒尾は約束された資金が得られず、梯子を外された形となり、以降財政難に苦慮することになった。
そのため、中心となるべき商社設立計画はやめ、付属教育組織であった日清貿易研究所を正面に据えた。これが幸いして、一八九〇年(明治二十三年)日本初はもちろん、世界初の国際的なビジネススクールの誕生となった。
当然、当初は学内に混乱がみられたが、盟友根津一の協力もあり、日的に沿う学校づくりが行なわれ、一八九二年には八九名の卒業生を輩出した。そして卒業後も商品陳列所で数十人の卒業生が実習を続けた。
しかし、この二年後、日清戦争が勃発すると、清語(中国語)を学んでいた卒業生は軍の通訳や偵察役に見込まれ、大本営からの要請に根津は商品陳列所の実習生に呼びかけた。その結果、多くの卒業生が通訳に参加したが、そのうち特に偵察役には七名が応じ、かつての「漢口楽善堂」出身者三名も加わった。こうして根津関係で十名が戦地へ向ったが、軍の訓練も受けていなかった卒業生たちは、以上十名のうち一名(向野堅一)を除いた九名が次々と捕縛され、斬首、銃殺されたほか行方不明者も出て、命を落した。戦争で日本が勝利し、根津は勢いを得て帰国したが、次々と届く有能であった教え子たちの悲惨な最後の悲報に痛恨のショックを受け、軍籍を離れると、ここ京都若王子の寓居に隠棲し、部屋には亡くなった卒業生たちの鎮魂に仏壇と位牌をつくって祀り、朝晩の読経をつとめ、取り残された子弟の養育も行い、このあと四年ほど禅の修行も行った。
一方、荒尾は開戦とともに軍籍を離れてこの若王子の寓居で過し、日本が戦争に勝利しても清国へ賠償金や領土割譲を要求すべきではないと『対清意見』と『対清弁妄』を執筆した。その要求を通せば清国民に重税が課せられ、日清貿易どころではなくなるという理由からであった。そこに荒尾の本気の姿勢があった。それはのちに同志社大学総長となる牧野虎次が卒業時に自校以外で唯一の恩師として仰いでいた荒尾をここ若王子に訪ね、教誨師として「北海道集治監」へ就職する報告をした時、荒尾は「石鹸」と大書した揮毫を贈り、「石鹸は自ら消えて相手の垢を落す」と説かれた人生観に牧野は感慨無量になったというエピソードにも重なる。
こうして、二人とも軍籍を脱ぎ、根津は荒尾に相談し、一八九六年(明治二八年)この若王子の寓居の隣接地に、「征清殉難九烈士」と題して亡くなった九人の霊の鎮魂とその顕彰を込めたこの碑を建立した。文は根津が綴り、書は力強く荒尾の筆であらわされた。
九烈士は次の通り
漢口楽善堂出身者
・藤島武彦(鹿児島) 杭州で落命 享年二十六歳
・石川伍一(秋田) 天津で落命 享年二十九歳
・山崎羔三郎(福岡) 金州で落命 享年三十一歳
日清貿易研究所出身者
・藤崎秀(鹿児島) 金州で落命 享年二十三歲
・大熊鵬(福岡) 大孤山・消息不明 享年二十五歳
・猪田正吉(福岡) 大孤山・消息不明 享年二十六歳
・鐘崎三郎(福岡) 金州で落命 享年二十六歳
・福原林平(岡山) 南京で落命 享年二十七歳
・楠内友次郎(熊本) 南京で落命 享年三十歳
二〇二五年(令和七年)十一月
愛知大学
近衛篤麿の撰文による荒尾精への追悼碑文にも記されているように、荒尾精は当初軍人教育を受けたが、隣国の清が西欧列強に蚕食されつつある実態を知り、その対抗策は日清間の貿易を発展させ相互の経済力を強めることだとの考えに至った。こうして一八八六年(明治十九年)、念願かなって単身上海へ渡った荒尾は、すでに上海で国際商人として活躍していた日本人、岸田吟香の協力援助により、長江を遡った漢口に岸田の支店「漢口楽善堂」を開店し、岸田から提供された目薬や書籍、雑貨を販売し、清国での商取引体験を始めた。
そのさい、荒尾は、一八七七年(明治十年)に西南戦争で敗れた薩摩と肥後の若者や幕末に官軍に敗れた会津藩などの若者で、日本での出世をあきらめ渡してきた二十余名ほどを「漢⊂楽善堂」のメンバーとして集め、清国の商慣習を体験させるとともに商品販売や関係情報を収集整理もする私塾も設けた。商人となった若者達は商品を背負い各地へ出かけたが、不審者への警備が厳しい中、命を落したり、行方不明者が次々に出て、この試みには困難も多かった。
しかし、荒尾が三年半に及ぶこの清国での滞在中に収集した情報は多く、それらはこのあと盟友根津一(のち書院初代院長)の手で編纂され、『清国涌商綜覧』という商業地理的大著にまとめられ刊行された。初めて清国の実態を知った読者の評判となり、ベストセラーとなったほどであった。
荒尾はこれらの実績をふまえ、帰国後本格的な日清間の貿易事業人養成のための商社と学業の設立構想を明治政府に提案し、農商務省など関係大臣の支持を得た。そこで荒尾は早速全国を遊説し、日清間の貿易の重要性と将来性を学徒たちに説き、志願者を求め、うち選抜した一五〇人を連れ、関係者一同と共に上海へ向った。
しかし、折から支持してくれた岩村農商務省大臣は突然病気で辞任し、内閣も解散となり、荒尾は約束された資金が得られず、梯子を外された形となり、以降財政難に苦慮することになった。
そのため、中心となるべき商社設立計画はやめ、付属教育組織であった日清貿易研究所を正面に据えた。これが幸いして、一八九〇年(明治二十三年)日本初はもちろん、世界初の国際的なビジネススクールの誕生となった。
当然、当初は学内に混乱がみられたが、盟友根津一の協力もあり、日的に沿う学校づくりが行なわれ、一八九二年には八九名の卒業生を輩出した。そして卒業後も商品陳列所で数十人の卒業生が実習を続けた。
しかし、この二年後、日清戦争が勃発すると、清語(中国語)を学んでいた卒業生は軍の通訳や偵察役に見込まれ、大本営からの要請に根津は商品陳列所の実習生に呼びかけた。その結果、多くの卒業生が通訳に参加したが、そのうち特に偵察役には七名が応じ、かつての「漢口楽善堂」出身者三名も加わった。こうして根津関係で十名が戦地へ向ったが、軍の訓練も受けていなかった卒業生たちは、以上十名のうち一名(向野堅一)を除いた九名が次々と捕縛され、斬首、銃殺されたほか行方不明者も出て、命を落した。戦争で日本が勝利し、根津は勢いを得て帰国したが、次々と届く有能であった教え子たちの悲惨な最後の悲報に痛恨のショックを受け、軍籍を離れると、ここ京都若王子の寓居に隠棲し、部屋には亡くなった卒業生たちの鎮魂に仏壇と位牌をつくって祀り、朝晩の読経をつとめ、取り残された子弟の養育も行い、このあと四年ほど禅の修行も行った。
一方、荒尾は開戦とともに軍籍を離れてこの若王子の寓居で過し、日本が戦争に勝利しても清国へ賠償金や領土割譲を要求すべきではないと『対清意見』と『対清弁妄』を執筆した。その要求を通せば清国民に重税が課せられ、日清貿易どころではなくなるという理由からであった。そこに荒尾の本気の姿勢があった。それはのちに同志社大学総長となる牧野虎次が卒業時に自校以外で唯一の恩師として仰いでいた荒尾をここ若王子に訪ね、教誨師として「北海道集治監」へ就職する報告をした時、荒尾は「石鹸」と大書した揮毫を贈り、「石鹸は自ら消えて相手の垢を落す」と説かれた人生観に牧野は感慨無量になったというエピソードにも重なる。
こうして、二人とも軍籍を脱ぎ、根津は荒尾に相談し、一八九六年(明治二八年)この若王子の寓居の隣接地に、「征清殉難九烈士」と題して亡くなった九人の霊の鎮魂とその顕彰を込めたこの碑を建立した。文は根津が綴り、書は力強く荒尾の筆であらわされた。
九烈士は次の通り
漢口楽善堂出身者
・藤島武彦(鹿児島) 杭州で落命 享年二十六歳
・石川伍一(秋田) 天津で落命 享年二十九歳
・山崎羔三郎(福岡) 金州で落命 享年三十一歳
日清貿易研究所出身者
・藤崎秀(鹿児島) 金州で落命 享年二十三歲
・大熊鵬(福岡) 大孤山・消息不明 享年二十五歳
・猪田正吉(福岡) 大孤山・消息不明 享年二十六歳
・鐘崎三郎(福岡) 金州で落命 享年二十六歳
・福原林平(岡山) 南京で落命 享年二十七歳
・楠内友次郎(熊本) 南京で落命 享年三十歳
二〇二五年(令和七年)十一月
愛知大学